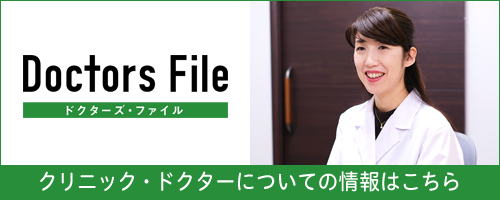高血圧とは
血圧とは、心臓が血液を血管へ送り出す際に血管壁にかかる圧力を指します。この血圧の値が慢性的に高い状態が続くと高血圧と診断されます。診断の基準としては、診察室での血圧と家庭での血圧で若干異なります。診察室での血圧は140/90㎜Hg以上、家庭での血圧は135/85㎜Hg以上を高血圧と診断します。
高血圧は、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。しかし、長期間放置すると心臓に余分な負担がかかり、血管が常にダメージを受けることになります。この影響で動脈硬化が進行し、さらには脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害、虚血性心疾患、心不全、腎臓病(腎硬化症など)といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
高血圧の原因は大きく2つに分けられます。ひとつは、本態性高血圧と呼ばれるもので、日本人の高血圧患者の約8~9割を占めています。このタイプの高血圧は特定の原因を断定することが難しいものの、遺伝的要因や生活習慣(過食、塩分過剰摂取、運動不足、飲酒、喫煙、ストレスなど)が影響していると考えられています。もうひとつは二次性高血圧で、甲状腺や副腎の疾患、睡眠時無呼吸症候群の患者に多く見られます。これらの基礎疾患が原因となる高血圧では、病気の管理が重要になります。
治療について
血圧の管理を徹底し、合併症の発症を防ぐことが重要です。
家庭血圧が135/85㎜Hgを超える場合、まずは生活習慣を見直します。その後、3〜6ヵ月経過しても改善が見られない場合や、高リスク患者では薬物治療が勧められます。
生活習慣の見直しでは、特に減塩が欠かせません。1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されています。
しかし、日本人の平均的な摂取量は10~11gとされており、達成するのは容易ではありません。そのため、出汁や酢を活用して味付けを工夫するなどの方法で塩分量を調整することが望ましいです。さらに、体内の塩分排出を促進するため、カリウムを含む野菜や果物を積極的に摂ることも有効です。また、肥満がある場合は心臓への負担を軽減するため、減量も必要になります。BMI25未満をにすることが目標です。
- 減塩:食塩摂取量6g未満/日を推奨(日本人平均は約10g)
- 体重管理:BMI25未満を目標
- 有酸素運動:週に150分以上の中等度運動(例:早歩き)
- 節酒:男性20〜30g未満、女性10〜20g未満のアルコール量を目安に
- 禁煙:必須事項として明記