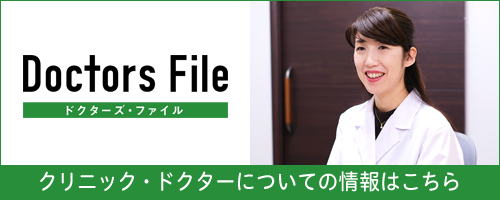糖尿病とは
糖尿病とは、血液中のブドウ糖が慢性的に基準値を超えた状態を指します。脳や体のエネルギー源であるブドウ糖は、通常、細胞に取り込まれてエネルギーとして利用されますが、その際に重要な役割を果たすのが膵臓で作られるホルモンの一種、インスリンです。インスリンは血液中のブドウ糖を細胞に運び入れる働きを担っています。しかし、何らかの原因でインスリンが十分に機能しなくなると、ブドウ糖が血液中に過剰に滞留し、結果として血糖値が慢性的に高い状態となります。この状態が続くことで、糖尿病と診断されることになります。
診断基準について
血糖値の測定には血液検査が用いられ、血糖値とHbA1cの数値を確認します。診断基準については以下の通りです。
- 血糖値が異常と判定される数値:早朝空腹時血糖値が126mg/dL以上、または75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値か随時血糖値が200mg/dL以上の場合
- HbA1cが異常と判定される数値:HbA1c値が6.5%以上の場合
上記2つの数値がどちらも基準値を超えている場合、糖尿病と診断されます。なお、血糖値かHbA1cの数値のどちらかのみ上回っているという場合は、糖尿病型と判定され、再検査が求められます。再検査の結果、どちらか一方の異常値が再度確認された場合には、糖尿病と診断されます。このため、一度の検査結果だけで判断するのではなく、複数回の検査を通じて正確な診断が行われます。糖尿病の早期発見と管理のためにも、定期的な検査を受けることが重要です。
糖尿病の種類
糖尿病は、インスリンが適切に分泌されないことによって発症しますが、その原因には大きく2つのタイプがあります。まず、1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が自己免疫反応などによって破壊されることで、インスリンの分泌がほとんどなくなる状態を指します。一方、2型糖尿病は、日本人の糖尿病患者の9割以上を占める病型であり、肥満や過食、運動不足などの生活習慣が膵臓に負担をかけることでインスリンの分泌が低下する、または分泌量が十分でもインスリンの働きが弱くなる(インスリン抵抗性)ことで血糖値が高くなる状態です。
さらに、糖尿病にはほかにもいくつかのタイプがあり、膵炎や膵臓がん、肝硬変などの病気、内分泌系の疾患、ステロイド薬の使用などが原因となる二次性糖尿病や、妊娠時のホルモン変化によって血糖値が上昇する妊娠糖尿病があります。糖尿病の発症要因はさまざまですが、早期に適切な管理を行うことで健康維持につなげることが可能です。
なお糖尿病も他の生活習慣と同様に自覚症状が出にくい病気として知られています。そのため病状を進行させやすくなるわけですが、ある程度まで進むと異常な喉の渇き、頻尿・多尿、全身の倦怠感、体重の減少といった症状がみられるようになります。
治療について
糖尿病の治療の目的は、血糖値の慢性的な上昇を抑え、合併症の発症を防ぐことです。なお、1型糖尿病と2型糖尿病では治療のアプローチが異なります。
1型糖尿病の患者様は、インスリンの分泌がほとんどないため、血糖値を適切に管理するためにインスリン注射を行います。これにより、血液中のブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギーとして利用することが可能になります。
一方、2型糖尿病の患者様は、インスリンがわずかに分泌されているため、まずは生活習慣の見直しを行うことが重要です。規則正しい食生活を心がけ、食べ過ぎを防ぎ、適正なエネルギー摂取量を守ることが推奨されます。また、栄養バランスの取れた食事を意識し、食品交換表を活用することで、血糖値の安定を図ります。さらに、運動療法も有効で、血糖値を下げる効果が期待できます。息が弾む程度の有酸素運動として、1回30分ほどのウォーキングが適しており、できるだけ日課として継続することが望ましいです。ただし、運動を始める前には医師に相談し、自身に合った方法を選ぶことが重要です。
生活習慣の改善だけでは血糖コントロールが難しい場合には、薬物療法を併用することになります。経口血糖降下薬が用いられ、インスリンの分泌を促進するものや、インスリンの抵抗性を改善するものなど、患者様の病状に合わせた薬が選択されます。それでも血糖値の管理が十分でない場合には、1型糖尿病の患者様と同様にインスリン注射による治療が必要になることもあります。