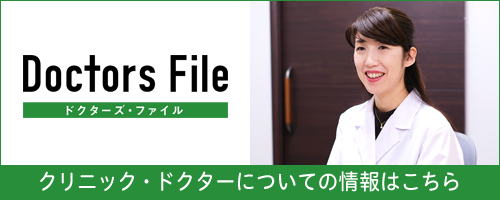脂質異常症とは
血液中の脂質(血中脂質)のうち、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)の数値が異常に高い、またはHDL(善玉)コレステロールの数値が基準値よりも低い場合、脂質異常症と診断されます。
この疾患は、高LDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症、低HDLコレステロール血症の3つのタイプに分類されます。いずれの場合もLDLコレステロールが血管内に蓄積しやすく、動脈硬化の原因となります。さらに、放置すると血管が狭窄して血流が悪化し、最終的に血管が閉塞するリスクがあります。その結果、脳梗塞などの脳血管障害、狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症といった深刻な合併症を引き起こす可能性があります。診断基準につきましては、次の通りです。
- LDLコレステロール値≧140mg/dL(高LDLコレステロール血症)
- 中性脂肪≧150mg/dL(高トリグリセライド血症)
- HDLコレステロール値<40mg/dL(低HDLコレステロール血症)
脂質異常症の多くは、健康診断や血液検査の結果を通じて発症や異常に気づくことが一般的です。しかし、自覚症状がほとんどないため、気づかないまま放置され、脳梗塞や心筋梗塞などの合併症を引き起こすケースも少なくありません。そのため、コレステロールや中性脂肪の数値を定期的に確認し、異常が疑われる場合は早めに受診することが重要です。
治療について
脂質異常症を発症している、またはその予備群と診断された場合は、適切な治療と予防に取り組むことが大切です。この疾患には高LDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症、低HDLコレステロール血症の3つのタイプがありますが、まずはLDLコレステロールの数値を下げることを優先することで、HDLコレステロールや中性脂肪の数値の改善にもつながるとされています。治療と予防には、食生活の見直しや運動の習慣化が重要であり、必要に応じて薬物療法が併用されることがあります。継続的な健康管理を心がけることで、より良い状態を維持することが可能になります。
脂質異常症の治療・予防において最も重要なのは、日常の生活習慣の見直しです。特に食事療法が重要であり、コレステロールを多く含む食品の摂取を控えることが推奨されます。例えば、レバー、卵黄、脂身の多い肉、魚卵、乳製品などはコレステロール値を上昇させやすいため、食生活の管理が必要です。一方で、コレステロールが血管内に蓄積しないようにするため、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが重要となります。具体的には、野菜、きのこ類、海藻などが挙げられます。
また、中性脂肪の数値が高い方は食べ過ぎを避けることに加え、糖分を多く含む食品(甘いジュースやお菓子など)やアルコールの摂取を控えることで数値の改善が期待できます。さらに、低HDLコレステロール血症の患者様は、トランス脂肪酸を多く含む食品(マーガリンやショートニングなど)の過剰摂取がHDLコレステロールの減少につながるため、これらの食品を控えることが推奨されます。
生活習慣の改善に加えて、適度な運動を取り入れることも有効です。特に有酸素運動は、トリグリセライド(中性脂肪)の数値を下げ、HDLコレステロールの数値を上昇させる効果が期待されます。例えば、1日30分程度のウォーキングを継続することで血中脂質の改善に役立ちます。効果が実感できるまでには数ヵ月かかる場合もありますが、無理なく継続することが大切です。
それでもLDLコレステロール値が目標範囲まで下がらない場合は、スタチン系の薬などを用いた薬物療法が併用されることがあります。服用については医師の指示に従い、適切に管理することが必要です。定期的な検査を通じて自身の健康状態を確認し、適切な食生活や運動を継続することで、脂質異常症の予防と管理が可能になります。