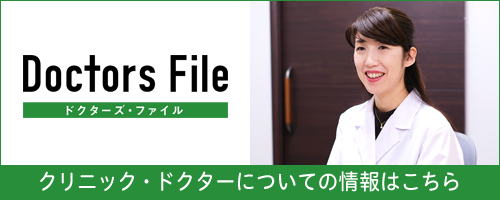認知症とは
認知症とは、脳の神経細胞が損傷したり機能が低下したりすることで、記憶や判断力、思考能力などの認知機能が持続的に低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。加齢によるもの忘れとは異なり、認知症では体験した出来事(例:朝食を食べたことを覚えていない 等)そのものを忘れてしまい、進行すると時間や場所の認識が難しくなることがあります。
認知症は、現時点で完治させる治療法は確立されていません。しかし、早期に気付き、適切な対策を講じることで進行を遅らせることが可能です。また、認知症の中には治る認知症もあります(ビタミン不足、甲状腺機能異常などによるもの)。その為、血液検査を行うことで、原因を見つけ、解決することもあります。
以下のような症状が見られる場合は、当院を一度ご受診ください。同居するご家族の方からのご相談にも対応いたします。
認知症が疑われる主な症状
- 物忘れがひどい(数分前、数時間前のことを忘れる、同じことを何回も聞く・言う、約束をすっぽかす 等)
- 時間や場所がわからない(曜日や日付がわからなくなる、通い慣れている道を忘れる 等)
- 理解力、判断力の低下(家電の使い方がわからなくなる、各種手続きやATMの引き出しなどができない、複雑な話が理解できない、善悪の判断がつかない 等)
- 身だしなみを気にしなくなる、部屋が片付けられなくなる
- 幻覚症状がみられる
- 趣味や好きなことに関心がなくなっている(意欲低下)
- 強い不安感がみられる
認知症の種類
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症とは
認知症の中で最も患者数が多く、認知症患者の半数以上を占めるタイプです。この疾患は、アミロイドβと呼ばれる異常なタンパク質が脳内に蓄積することで発症し、神経細胞が脱落していきます。側頭葉の内側にある海馬という記憶の部分の萎縮が特徴的で、その後徐々に脳全体の萎縮が進行します。進行すると、記憶障害だけでなく、妄想(ものとられ妄想)や不穏・暴言・暴力・徘徊・介護拒否など周辺症状(BPSD)が強くなっていきます。周辺症状が強くなってくると介護の負担も大きくなってくる為、周辺症状が出ないような対策が必要です。当院では、そのような時にどうしたらよいか、アドバイスを行っていきます。進行する前から、ご家族様がご本人様に対して笑顔で接するように心がけることがポイントです。もの忘れをすることに対して、怒った表情をしたり、問い詰めると、不安が大きくなり攻撃的になっていくことがあります。ご家族が適切な対応を行っていても、どうしても周辺症状が強くなっていくことが避けられない場合もあり、その時には抗精神病薬や漢方などを使って症状の緩和を目指します。
アルツハイマー型認知症と診断される前の段階で軽度認知機能障害(MCI)という状態もあります。MCIとは、もの忘れの症状はみられるものの、まだ日常生活に支障をきたすほどではない状態です。MCIの方が皆、アルツハイマー型認知症に移行するわけではありません。MCIの状態から約1/3が進行し、1/3がそのまま維持、1/3が正常に戻るという報告があります。現在では、MCIの段階から治療をはじめることも検討されています。脳に溜まりつつあるアミロイドβを除去する抗アミロイドβ抗体薬による直接的な治療です。日本では、2023年にレカネマブ、2024年にドナネマブという2種類の注射薬が承認されています。この薬は、早期のアルツハイマー型認知症とMCIの方に適応があります。まず、本当に脳にアミロイドβが溜まっているか確認してからの治療になります。千葉県内で投与できる医療機関が決まっており、ご希望がある方で適応の可能性がある方は、当院からそのような医療機関にご紹介させていただきます。そこで、投与が開始され、安定した方は、当院に通院しての投与継続もご相談させていただきます。
治療に興味のある方は、副作用などのお話も含めてさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
アルツハイマー型認知症の治療としては、大きく2種類あります。1つは、脳の神経が少なくなって減少してしまったアセチルコリンという神経伝達物質をコリンエステラーゼ阻害薬という薬で、増やす治療です。分泌されたアセチルコリンがすぐに減らないように、代謝する物質を抑えることで、アセチルコリンを増やします。飲み薬やゼリー、パッチなどがあります。副作用は吐き気が出ることです。その他は心臓の脈が遅くなったりすることがあります。当院では、心電図や脈をチェックしながら使用し、吐き気の副作用に対してもアドバイスを行っていきます。
2つ目の薬は、メマンチンという薬です。こちらは、脳の中のグルタミン酸という物質による過剰になった刺激を抑制することで脳内のノイズを除去し、異常行動を落ち着かせるとされています。
この2つの薬は併用することが可能です。
これらは、現段階の症状を改善するだけでなく、進行を2~3年遅らせるという進行抑制作用もあるとされています。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症とは
レビー小体型認知症とは、幻視が見えることとパーキンソン病のような身体の固さや動きにくさが出るということの2つの特徴をもつ認知症です。幻視は認知症の進行期やパーキンソン病の進行期にもみられますが、レビー小体型認知症の場合は、早い段階から、はっきりとした幻視(見えないはずの動物や人、虫などが見える)が見えるようです。
また、幻視が強く見えるタイプとパーキンソン病の症状が強く出るタイプと幅があります。経過の途中で、突然意識がなくなったように寝てしまったりする(意識の変容)特徴や、夜中に大きな寝言や大きな動きを伴うレム睡眠行動異常症といった症状を伴うこともあります。
レビー小体型認知症の治療は、アルツハイマー型認知症と同じ薬が保険適応になっているものもあります。また、症状に合わせて、幻視に対する抗精神病薬やパーキンソン病の薬を使用します。
脳血管性認知症
脳血管性認知症とは
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因で発症します。これらの疾患により脳内の血管が詰まったり破れたりすると、血液の循環が悪化し、脳の一部に十分な酸素や栄養が供給されなくなります。その結果、該当する部分の脳細胞が壊死し、その影響で認知症の症状が現れるようになります。この状態を脳血管性認知症と言います。
はっきりとした脳梗塞の既往がなくても、徐々に小さな脳梗塞が集まって影響を及ぼしてくることがあります。血圧の変動も原因となります。
症状の程度や進行状態は、障害を受けた脳血管の部位によって異なりますが、脳血管障害が再発すると症状が悪化する傾向があります。記憶障害や実行機能障害がみられることが多く、認知機能が部分的に損なわれるため、まだら状に症状が現れるのが特徴です。加えて、手足のしびれや麻痺、うつ症状、急に泣いたり怒ったり感情のコントロールが困難になるなどの症状も見られることがあります。
脳血管障害の多くは、動脈硬化が原因となって発症しますが、原因となる動脈硬化が進まないような予防策が大切です。その主な要因は生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)によるものです。そのため、血液をサラサラにする抗血小板薬や糖尿病治療薬、コレステロールや中性脂肪を下げる薬などこれらの疾患の適切な治療を行いながら、日常のライフスタイルを見直し、健康管理を徹底していくことが重要となります。
もの忘れの受診について
軽度のもの忘れの相談
日常生活でもの忘れが気になる方は、お気軽にご相談ください。当院にて、問診、神経学的検査、認知機能検査を行い、必要に応じて、認知症採血、頭部MRI画像等をご案内します。
中等度~重度のもの忘れの相談
ご本人様ではなく、ご家族様が困られているケースが多いです。ご本人様だけの受診では、受診内容を忘れてしまうことも多く、おうちでの日常生活の様子もお伺いしたいため、必ずご家族様同伴でご受診ください。
ご本人様が受診に来たがらない場合
認知症のケースでは、ご本人様が診察に拒否的で、病院や診療所まで連れて来られない場合があります。その際、ご家族様のみでの相談にも応じます(自費診療となる場合があります)。お電話にてお問合せください。
認知症にかかわる書類
当院では以下の書類の作成を承っております。いずれの書類も初診のみでは作成することが困難な場合が多く、数回受診していただく必要があります。時間に余裕をもってご相談ください。
運転免許更新にかかわる診断書
免許更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査を受けた方のうち、「認知症のおそれがある」と判定された場合、認知症に関する医師の診断書を提出する必要があります。対象の方には「診断書提出命令書」が送付されます。当院では、命令書に同封の「診断書(公安委員会提出用)」を記載することが可能です。
成年後見制度における診断書
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人(「後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。その際、申立書とともに提出する書類の1つに医師が作成する「診断書」があります。当院ではこちらの診断書の作成が可能です。